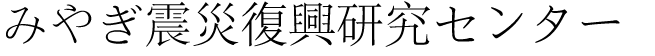先日,東日本大震災被災者向けに仙台市が供給した災害公営住宅入居者のうち,収入超過となった世帯(収入超過者)に対して課す明け渡し努力義務と割増家賃が,被災者の生活再建や,災害住宅のコミュニティ形成・維持の重大な障害になっていることについて,その違法性を主張するブログを投稿した。その中で指摘したように,被災自治体の収入超過者対応のあり方に決定的なインパクトを与えたのが,2017年11月17日に被災3県災害公営住宅担当部局宛に発した事務連絡である。復興庁は,同事務連絡において,国が既に災害公営住宅の家賃対策のために行なっている格段の支援を用いて,被災自治体が独自の判断で対応すべきだと国の立場を明らかにした。私は,東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター(みやぎ県民センター)の元に設置された「住まい」プロジェクトチーム向けに,国の言う「格段の支援」の意味を考察した文書を,復興庁事務連絡発出直後の12月に執筆した。それをこのブログで紹介しておきたい。当初の執筆日時は,2017年12月26日であるが,何点か誤りがあって,その後数回改訂している。
なぜ,「災害公営住宅家賃低廉化事業」交付金が自治体にとって黒字になるのか
2017年12月26日
遠州尋美
「災害公営住宅家賃低廉化事業」のための交付金が大幅な黒字になり,交付を受けた自治体を潤していることについて,災害公営住宅の家賃問題に関わっている議員や専門家でも十分に理解していないと考えられる。そこで,制度設計上黒字になることが必然であることを説明したい。
1.公営住宅家賃低廉化補助の考え方
公営住宅は住宅に困窮する低所得者に対して自治体が提供するものであることから,入居者の支払い能力と受益とを勘案して市場家賃から家賃の減免を行う「応能応益家賃」制度を採用している。そのため公営住宅を提供する自治体の家賃収入は,住宅の用地買収や建設にかかる費用,運用開始後のメンテナンスや管理を賄うには不足し,その不足分が自治体の負担となって自治体財政を圧迫することが考えられる。そのため,自治体の公営住宅供給意欲を減退させ,供給不足を生じさせることが懸念される。そこで,「応能応益家賃」による家賃収入の不足を補うため,市場家賃から減額した家賃収入の一部を運用開始から20年間にわたり国が補助するのが公営住宅家賃低廉化補助である。一般の公営住宅の場合,その補助率は1/2であるが,災害公営住宅においては特例として,激甚災害の場合当初5年間3/4,その後の15年間は2/3,東日本大震災の場合は,当初5年間は7/8,その後の15年間は5/6となる。しかも,東日本大震災では自治体負担の一層の軽減のため,その負担分についても地方交付税でカバーするという手厚いものとなった。しかし,家賃収入の不足による財政負担の緩和という目的を字義通りに解釈すると,それがなぜ大幅な黒字となるのか理解することは困難であろう。そこで,民間賃貸住宅の経営における家賃設定を事例としてその理由を説明する。
遠州註:公営住宅法第17条では,公営住宅の管理開始の日より5年以上20年以内の期間,近傍同種家賃と入居者負担基準額の差額の2分の1を補助することになっている。この資料でのモデル計算は,この通り家賃低廉化補助が行われていたという前提での計算である。三位一体改革により,2004年以前に建設された公営住宅に関する公営住宅家賃低廉化補助は公営住宅法の規定を変えることなく一般財源化され,地方交付税としては自治体に配分されることになった。ただし,2005年以降に建設された公営住宅については,地域住宅交付金を経て現在は社会資本整備総合交付金に引き継がれて,法に定められた形で家賃低廉化補助が行われている。従って,三位一体改革を経たのちも,この資料の議論に誤りはない。
2.民間賃貸住宅における家賃の設定
ここで,理解しやすいように,以下のような仮想のモデルを考える。賃貸住宅の経営を行う個人Aがいる。Aは,都市計画上の容積率300%,平米単価25万円の土地800平米を2億円で取得し,その上に集合住宅を建築し賃貸する。容積率は300%なので建築可能な建物の延べ床面積の上限は,2400平米である。建物のうち廊下,エレベーター,階段室,玄関ホール,管理事務所などの共用空間は約20%程度なので,住戸部分の面積はおよそ1900平米となり,65平米の住宅であれば30戸の住宅を建築できる。鉄筋コンクリート造の住宅の標準的な建設費は1平米あたり24万円なので,建築費は5億7600万円となる2)。すなわち,初期投資として7億7600万円が必要である。鉄筋コンクリート住宅の法定耐用年数は47年だが,実際には陳腐化等の理由で35年程度で建て替えられることが多い。そこでAは35年で償却する前提で資金調達を行う。すなわち,金融機関から返済期間35年,金利3.5%で,全額融資を受け,毎年1回元利均等払いで返済する1)。したがって,Aはこの建設費7億7600万円を利子を含めて返済し,その間のメンテナンス費用,管理費用,固定資産税等(それらを合わせて「管理経費」と呼ぶ)を支払い,かつ他へ投資した場合と同等もしくは上回る利益をえるにたる家賃を設定しなければならない。ここでは期待投資利回りを5%とする。常に全戸が供用されるわけではないので,平均の空き家率を20%(入居率80%)と見込む。また平均の管理経費は,空き家であるなしにかかわらず1戸あたり年間25万円,総額年750万円であると仮定する。すなわち
- 初期投資:7億7600円(期間35年,年利率3.5%,元利均等払(年1回期末払い)で全額金融機関の融資)
- 管理経費:年750万円
- 期待収益:$Σ(借り入れ残高×5%(年))$
- 家賃収入:$X×24戸(年)$(戸あたりの家賃収入をXとし入居率を80%とした場合)
$$(X×24×12×35)>(7億7600万円+利子総額+750万円×35+Σ(借り入れ残高×5%(年)))$$
となるように$X$を定めることになる。
以上のモデルに対してそれぞれを計算すると以下のようになる。
- 毎年の返済額3千879万8718円
- 返済総額13億5795万5130円
- 管理経費の総額2億6250万円
- 期待収益の総額(35年間)6億3833万5883円
したがって,確保すべき家賃収入の35年間の合計は22億5879万1013円
空き家率20%として,1戸あたりの月額家賃は,22万4086円となる。要するに,家賃22万円〜23万円程度に設定できるならば,Aは賃貸住宅経営に踏み出すことができる3)。
【注】
- 賃貸住宅向け長期融資の金利は金融機関によりまちまちで2.5%〜5%に分布している。通常は元利金等返済若しくは元金均等返済で毎月返済することが一般的であるが,ここでは簡単のために年1回の返済とした。
- RC造住宅の坪単価は,およそ65万円〜95万円の間に分布している。
- 因みに不動産経営における利回りは,投資額に対する年間の家賃総額を指すので,家賃22万4086円の利回りは8.3%となる。リーズナブルな水準である。
3.建築費補助がある場合の損益分岐家賃
ところで,ここに公営住宅と同じように建築費について1/2の補助があったと想定してみよう。Aにとっては,経営に踏み出すかどうかを判断する家賃,すなわち損益分岐家賃はどうなるだろうか。補助金2億8800万円を減じた4億8800万円を初期投資として,上記で行なった計算を行えばよい。結論だけを書くと,月額家賃15万585円で成り立つことになる。すなわち,このモデルの場合,建築費の2分の1補助で,損益分岐家賃は当初の市場家賃から3分の1低減される。
- 毎年の返済額2千439万9194円
- 返済総額8億5397万1790円
- 管理経費の総額2億6250万円
- 期待収益の総額(35年間)4億142万7718円
- 確保すべき家賃収入の総額15億1789万9508円
上記の市場家賃の算定方法は,公営住宅法でいう近傍同種家賃の計算式にのっとったものではないが,そう大きくは違わないはずである。仮に,近傍同種家賃と上記市場家賃が一致しているとすれば,近傍同種家賃から大幅に(例えば3割程度)下回る上限家賃(退去を拒む高額所得者が支払うべき家賃)を設定したとしても,民間賃貸住宅経営の立場で判断しても何ら自治体財政を圧迫するものではないことがわかる。
4.公営住宅の損益分岐家賃
しかし,公営住宅の場合には損益分岐家賃はさらに下がることになる。公営住宅の場合は民間賃貸住宅経営とは異なり,建設費は税収を持って当てれば良い(起債による選択肢もある)からである(遠州註:平成30年2月26日適用の地方公共団体金融機構の長期貸付金利は,30年固定金利・半年賦元利均等返済の場合,基準金利0.65%である。民間向け市場金利よりはるかに安い)。すなわち,上記Aが支払った銀行利子3億6597万1756円は支払う必要がない。また,公営住宅は収益事業ではないので,期待収益4億142万7718円も不要である。すなわち,公益事業である公営住宅建設の場合は,補助金によって減額された初期投資金額と管理経費の合計7億5050万円を35年間で回収できる家賃収入さえあれば良い4)。すなわち,上記の集合住宅モデルを公営住宅として供給する場合の損益分岐家賃は,7万4454円となる。すなわち民間賃貸住宅経営の場合と異なり,市場家賃の3分の1程度の上限家賃でも自治体財政を圧迫することはない。
ちなみに,東日本大震災における災害公営住宅補助は,通常対象とはならない土地の買収費も対象となり,補助率も7/8になっている。その上,自治体の負担分であるいわゆる補助裏も地方交付税で手当される(遠州註:この記述は誤り。公営住宅は家賃収入があるため,地方負担分に対する震災特交措置は省かれた。ただし公営住宅建設事業債(充当率100%,元利償還金に対する交付税措置はない)で措置される)。すなわち,上記のモデル例で言えば,管理経費分だけ賄うに足りる家賃収入があればよい。すなわち高額所得者に対する上限家賃であっても,月額2万6042円あれば自治体財政を圧迫しない。
【注】
- なお,地方自治体に固定資産税を課すことは地方税法が禁じているので,固定資産税分だけ管理経費も下がるがここでは無視するとする。
5.自体財政にとって不利な公営住宅の公募買取や借上げ
ここで,注意しておきたいのは,上記の公営住宅損益分岐家賃に関する指摘は,自治体が自ら発注して公営住宅を建設する場合である。公募買取や借上げにおいては,その説明は成り立たない。
まず,公募買取の場合は,建設する民間事業者は,建物完成後直ちに自治体に売却するが,その売却価格には当該民間事業者の利益が上乗せされている。同等の建物を自治体が自ら建設するときと比べてその利益だけ自治体は余分の支出を迫られる。
さらに自治体にとって不利なのは借上げ公営住宅である。借上げ公営住宅の貸主は通常の民間賃貸住宅経営者と何ら変わるところはないので,自治体は貸主に対して市場家賃で契約せざるを得ない。直接供給なら,通常の公営住宅でさえ損益分岐家賃は近傍同種家賃の3分の1程度に抑えることができる可能性が高いのに,借上げではまともに市場家賃,すなわち近傍同種家賃を負担しなければならないのである。
6.家賃低廉化補助が黒字になるからくり
ここでは,通常の公営住宅でさえ,家賃低廉化補助によって,自治体負担に黒字が生じる可能性を示す。再び,上記集合住宅モデルを使って検討する。運用期間は35年間である。そしてモデルの想定で計算した市場家賃が近傍同種家賃と一致していると考える。すなわち,近傍同種家賃は22万4000円(100円以下を切り捨て)である。また,自治体にとって財政負担とならない損益分岐家賃は7万4400円(100円以下を切り捨て)である。さらにこの住宅への入居者の収入分布を,現に仙台市の災害公営住宅における入居者の収入分布に近似していると仮定するする。すなわちそれぞれの階層の入居者数は次のようになる。
表1 モデル公営住宅の居住者収入分布
| 階 層 | 政令月収 | 家賃算定基 礎額 | 災害公営住宅の入居者分布 (2017 年 12 月4日,仙台市) | モデル住宅の入居 世帯数 |
| Ⅰ | 0~104,000 円 | 34,400 円 | 80.84% | 24 世帯 |
| Ⅱ | 104,001~123,000 円 | 39,700 円 | 4.11% | 2 世帯 |
| Ⅲ | 123,001~139,000 円 | 45,400 円 | 3.24% | 1世帯 |
| Ⅳ | 139,001~158,000 円 | 51,200 円 | 2.65% | 1世帯 |
| Ⅴ | 158,001~186,000 円 | 58,500 円 | 3.27% | 1世帯 |
| Ⅵ | 186,001~214,000 円 | 67,500 円 | 2.39% | 1世帯 |
| Ⅶ | 214,001~259,000 円 | 79,000 円 | 1.55% | 0 |
| Ⅷ | 259,001 円~ | 91,000 円 | 0.84% | 0 |
次に,各階層の家賃設定に関しては,家賃算定基礎額をそのまま家賃額とする。なぜなら,家賃算定に必要な市町村立地係数は,仙台市は1.0であり,規模係数は住戸が65平米なので1.0である。利便性係数は,公営住宅法施行令で0.5〜1.3の範囲で自治体が定めることとなっている。ただし,平成16年の改正以前は0.7〜1.0であったように,1.0を超えるのは基本的には都心部に限定すべきである。このモデルは,容積率は300%と商業地でも高めの数値を仮定したので,利便性係数は1.0とする。また,経過年数係数として毎年減ずる割合は十分に小さいので,ここでは無視することする。
さらに,常に入居率は100%であり,政令月収が158,000円を超える2世帯は裁量階層の条件を満たしており,したがって入居者の階層分布も変化しないものとする。この条件のもとで毎年の家賃収入を計算すると以下のようになる。
- 毎月の家賃収入:$34,400×24+39,700×2+45,400+51,200+58,500+67,500円=1,127,600円$
- 毎年の家賃収入:$1,127,600×12=13,531,200円$
- 運用期間全体の家賃収入:$13,531,200×35=473,592,000円$
すなわち,運用期間全体でおよそ4億7000万円の家賃収入がある。
一方,この住宅の損益分岐家賃は上述の通り7万4400円であり,その場合の入居率は80%を仮定していたから,運用期間全体の不足額は次のように計算される。
- 運用期間全体で必要な家賃収入:$74,400×24×12×35=749,952,000円$
- 運用期間全体での家賃収入不足額:$749,952,000−473,592,000=276,360,000円$
この不足額は,公営住宅家賃低廉化補助でどの程度カバーされるであろうか。
公営住宅家賃低廉化補助は,その事業目的を字義通りに解釈すれば,入居率100%,全ての世帯に近傍同種家賃を課すものとして計算する家賃収入と応能応益家賃による実際の家賃収入との差額に対し,その2分の1を20年間に渡って補助する(遠州註:実際は,空室,収入超過者入居住戸分は減額される。また実効補助率は45%程度)。上述の通り,近傍同種家賃は22万4000円であり,また,このモデルにおける毎月の家賃収入は112万7600円だから,20年間の補助額は次のように計算される。
- 年間の補助額:$(224,000×30-1,127,600)×12/2=33,554,400円$
- 20年間の補助額:$33,554,400×20=671,088,000円(空家率20%を見込んでいるので,正しくは,この金額の80%,即ち536,870,400円)$
なんと収益分岐家賃との関係で35年間の家賃収入不足額は2億7600万円であるのに対し20年間の家賃低廉化補助額は約6億7000万円(正しくは5億4000万円)と,概ね2倍半を超える金額となる。
これは一体何を意味するだろうか。最初のモデルをもう一度思い返してみよう。建築費は5億7600万円だった。これを35年後に建て替えるとする。土地は市の所有なのだから建て替えに土地買収は不要であり,必要なのは建設費である。一方,この建て替えにも当然国の2分の1補助がある。したがって,実際に必要な市の建設投資額は2億8800万円である。収益分岐家賃収入から補助額はおよそ4億円超過しているのだから,そこから建替え費用を差し引いても(すなわち建て替え基金に繰り入れても)なお,1億1000万円余る。すなわち,これを使って本来家賃に対する割引制度を作っても,建て替えに必要な資金を十分確保できるのである。ちなみに全世帯一律に割り引くとすれば,1世帯あたりの毎月1万円程度割り引くことができるのである5)。
【注】
- なお,建て替えに際して必要となる建設投資額も,実は家賃低廉化補助による基金ではなく,その時点における税収で賄ったとしても現行の低廉化補助事業が廃止されない限り何の問題もない。なぜなら,建て替え後の低廉化補助で十分にお釣りがでるはずだからである。ただし,低廉化補助が維持される保証はないので,建て替え資金のための基金にするということを否定する論拠としてはやや弱い。
7.まとめ
以上のモデル検討から,次のことが指摘できる。
① 運用期間を35年として一般の公営住宅を直接供給する場合,財政負担を生じさせない損益分岐家賃は,近傍同種家賃よりもはるかに低い。おそらく3分の1程度となる。
② 公募買取では損益分岐家賃は直接供給より高くなり,借上公営では近傍同種家賃を自治体は負担しなければならない。
③ 東日本大震災の特例により,災害公営住宅の収益分岐家賃は管理経費を賄うに足る金額となる。おそらく近傍同種家賃の15%以下となる。
④ 家賃低廉化補助は,一般の公営住宅の場合でさえ,直接供給するならば大幅な黒字となり,多くの場合35年後に建て替えることを想定しても建て替え費用を賄った上になお余剰が生じる。したがって,自治体財政に負担をかけることなく,その余剰分を用いて独自の家賃減免を行うことが可能である。
⑤ 東日本大震災家賃低廉化補助が大幅な黒字になるのは当然であり,災害公営住宅入居者の家賃減免だけでなく,一般の公営住宅向け家賃低廉化補助も活用して,従来の公営住宅も含めた包括的な家賃減免制度を作るべきである。
⑥ 特別減免は,10年目以降についても入居者が存命中は継続するべきであり,その財源は家賃低廉化補助で賄うことは可能である。
⑦ ただし,公募買取や借上公営では④の議論は成立しない。したがって,現在の国の制度が続く限り,自治体は公営住宅の直接供給に徹するべきである。
⑧ 裁量階層の収入基準は施行令による上限である25万9000円まで引き上げるべきであり,さらに本来階層の収入基準は施行令の参酌標準である15万8千円を上回る水準に維持されるべきである。
遠州註:耐火造の公営住宅は,一般の建物の法定耐用年限とは異なり,70年間とされている。ただし,耐用年限の2分の1を過ぎれば,公営住宅法上は建て替えが可能である。従って,35年で建て替えると言う設定は,公営住宅法に反していない。しかし,他方で公営住宅の長寿命化計画の策定を求められており,多くの自治体は耐火造公営住宅の耐用年限70年を前提とした長寿命計画を定めている。従って35年で建て替えると言う設定での議論には違和感を感じるであろう。しかし,現行の公営住宅長寿命化計画策定指針(2016年8月)では,LCC(ライフサイクルコスト)を長寿命化計画の基本とすることとしている。そこで,LCCの推計をどのように行うかが,既存の公営住宅の維持すべき期間の決定を左右する。通常の公共施設と公営住宅の決定的な違いは,潜在的入居者にとって,住宅市場に供されている他の住宅(例えば民間賃貸住宅)と比較考量する対象,すなわち商品だと言うことである。すなわち,躯体の構造的強度が使用に耐えるとしても,設備や内外装など構造的強度以外の要素が住宅商品として陳腐化し,市場のニーズにそぐわなくなれば,住宅としての価値は失われる。従って,修繕費用も新築時の躯体や設備等の物理的損耗を補って維持するだけではなく,住宅市場の変化に応じて設備の変更(例えば,情報通信環境の性能や環境性能,バリアフリー化,高齢化に伴う介護需要への対応)なども見込んで設定し,空室率を抑制するように計画して算定することが必要となる。その結果,LCCが最適化される維持期間は,70年よりははるかに短縮されるだろう。ここで厳密な計算を行うのは不可能だが,おそらくは,民間賃貸住宅の現実の建て替えサイクルを基礎として,新築時の建設補助や地方負担分の資金調達コストが民間住宅よりはるかに有利であることによって生じる延命効果を加味した年限に集約するであろう。ただし,LCCは,公営住宅制度の枠内で,今後も公営住宅に対する補助制度が存続すると言う条件下で計算するので,後者の部分は民間との競争は本来考慮しなくても良い。つまり,結局は,民間住宅の現実の建て替えサイクルにほぼ収斂するのではないか。すなわち,35年から45年程度が妥当であろう。
もう一点,注意しておかなければならないのは,社総公事業である公営住宅家賃低廉化事業の場合にも,地方負担分は基準財政需要の単位費用として普通地方交付税措置がなされている。単位費用措置なので,自治体ごとの公営住宅のストックの多寡とは無関係に平準化されることにはなるが,交付税措置があることは,公営住宅の直接供給は自治体財政の負担にはならないというこのブログの議論を補強するものである。