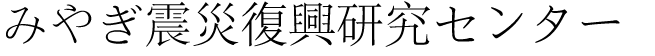『東日本大震災100の教訓 復興検証編』出版記念研究交流集会
検証なき復興フェードアウトに抗して
講演・報告録画映像を公開します
千葉昭彦(みやぎ震災復興研究センター代表・東北学院大学経済学部教授)
初動が遅れ被災者を苦難に陥れた能登半島地震。東日本大震災の教訓は正しく受け継がれたの。復興に向けた課題は何か。被災者の視点で大震災を検証する2日間のシンポが始まります。
深松 努(株式会社 深松組 代表取締役社長)
「地元に建設業が無くなってしまったら,不明者の捜索さえできませんよ。」東日本大震災発災直後から,仙台建設業協会副会長として,復旧・復興に携わった深松さんが,その経験をもとに熱く語ります。
増田 聡(研究交流集会実行委員長・東北大学大学院経済学研究科教授/震災復興研究センター長)
東日本大震災後も頻発する大災害。大震災後に,ほぼゼロから「復興計画」を策定し遂⾏体制の整備が進められてきた。私たちもその検証に取り組んだが,実務現場へのフィードバックは⼗分であったとはいえない。その議論を深める2日間。
長谷川公一(みやぎ震災復興研究センター副代表・尚絅学院大学特任教授)
誰のため何のための復興だったのか。災害救助は自衛隊に委ねていて良いのか。災害救助隊をつくるべきではないのか。長谷川公一さんが,第三者検証の重要性と現地再建の意義を論じています。
鈴木 浩(福島大学名誉教授・福島県復興計画検討委員会会長(当時))
今なお不安に苛まれている原発被災地からの長期避難者。長期かつ広域的な原発災害の苛酷さと「帰還から復興へ」という単線型復興シナリオとの齟齬。
被災者・県民が主体となるには,原発災害の苛酷さを踏まえた復興ビジョンの再構築が必要だ。原発災害と向き合い続けた鈴木浩さんが,「県民版復興ビジョン」づくりを提起する。
【第一セッション】パネルディスカッション 「取り残される被災者にどう向き合うのか」
年初に発生した能登半島地震。厳寒期の避難所環境は良好とは言えず,多数の在宅避難者が存在し,今なお命の危険にさらされている。住家被害調査に大量の人的リソース投入される一方で,最優先すべき被災者救済が手薄なのは否めない。なぜこんなことになるのか。どのような構想がこの現状を変えるのか。東日本大震災以降各地で取り組まれるようになった,一人ひとりに寄り添った被災者生活再建支援の手法である「災害ケースマネジメント」を主軸として議論したい。
菅野 拓(大阪公立大学大学院文学研究科准教授)
中心テーマは災害ケースマネジメント。元日に発生した能登半島地震,依然として奥能登は救急救命段階にあるものの,在宅被災者把握や災害ケースマネジメントも優先課題に位置付けられるようにはなっている。支援者として,報道人として,弁護士として,災害ケースマネジメントに深く関わった3人の問題提起を受けて,能登半島地震や国の動きも見据えながらディスカッションを。
伊藤健哉(一般社団法人チーム王冠代表)
津久井 進(弁護士・兵庫弁護士会)
中関武志(NHKエンタープライズ東北支社コンテンツ制作部シニア・プロデューサー)
「内閣府は教えてくれない 好事例で確認する災害ケースマネジメントの可能性」
災害ケースマネジメントは,発災直後から不可欠だ。避難所でも必要とされるものは,被災者本人に聞かなければわからない。現場に足を運んで被災者の声を「傾聴」し,その人に相応しい支援を届ける。自分ができないことは専門家の助けを借りる。あたりまえのことをするのです。東日本大震災で弁護士,医療関係者と4,000世帯に足を運んで災害ケースマネジメントを実践したチーム王冠の伊藤さんは言います。
「大震災後も発生し続ける取り残される被災者たち」
全国各地の災害現場で取材を重ねた中関さん。チーム王冠の密着取材は,「在宅被災者」の存在を知らしめ,国が防災基本計画に災害ケースマネジメントを位置付けるきっかけを作った。取材経験から思うのは,個別の災害ごとに予算と配分先が決まる災害復興制度の枠組みで「⼈間の暮らしの再建」をカバーするのは無理がある。福祉との融合は不可⽋だが,福祉現場でも取り残される人がいる。社会保障全体の⾒直しが迫られているのではないか。
「災害ケースマネジメントの課題」
災害ケースマネジメントを唱導する津久井進さんの明快な解説。国の防災基本計画に位置付けられたが,能登地震後の対応をみると本旨が十分理解されていると言い難い。制度を「正しく」運用すると制度の隙間に落ちて取り残しが起きる。制度の限界があらわとなる。そこで大事なのが,罹災判定に縛られず一人ひとりのリアルをみる。課題解決型ではなく,アウトリーチで伴奏型支援,福祉と連携して一人ひとりのくらしの実態を検証し,「餅屋は餅屋」,よってたかって支援する。最も大切なのは目的が生活再建の実現にあることを忘れない。生活再建が達成されるまで,寄り添い続けることが大切だ。
「取り残される被災者とどう向き合うのか」
災害ケースマネジメントの実践において,「寄り添う」とはどういうことか,「寄り添う」役割を担う主体とは,「取り残される被災者」をどうやって把握するのか,平時から災害時を見据えた取り組みはできるのか。討論者の須沢栞さんの問題提起は,どのように深められたか。
【第二セッション】
パネルディスカッション
「復興まちづくり再考 『職住分離』『高台移転』がもたらした復興の姿」
人の住まない荒地を守る防潮堤,広大な非可住地,追い立てられた被災者,巨費を投じて造成された限界集落など,復興まちづくりを経た被災地の実態を,客観的データで具体的に示すとともに,復旧・復興事業制度の瑕疵とその運用にのめり込む官僚主義を検証し,また,住民自治の可能性を示した数少ない事例も踏まえて,被災者が復興の主体となり得るには何が必要か,議論したい。
田中正人(追手門学院大学地域創造学部教授)
復興の主体は誰か。災害リスクの受容∕回避を判断するのは誰か。東⽇本⼤震災の被災地では,沿岸部に広く災害危険区域が指定され,居住が制限されることとなった。他⽅,その移転⽤地として,内陸・⾼台には無数の造成地が建設されてきた。津波で破壊された防潮堤は,わずかな例外を除き,よりハイスペックな防御設備して海岸線を埋め尽くしている。⽔際で防御しつつ,あらかじめリスクから撤退しておくという論理には⼀定の合理性がある。問題は,この判断が基本的に国家主導で⾏われたという点にある。それを今後も踏襲するのか。大震災復興の現実を踏まえ議論したい。
阿部重憲(新建築家技術者集団宮城支部・都市プランナー)
小川静治(東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター事務局長)
遠州尋美(みやぎ震災復興研究センター事務局長・元大阪経済大学教授)
「復興まちづくりがもたらしたもの」
大震災の復旧・復興支援を続けてきた小川静治さんが示す復興の現実。総延長433km,1兆3621億円を費やした防潮堤。背後には人家のない荒地が目立つ。1区画当り最大1.9億円,平均6.7千万円を費やしながら対象世帯の3分の1の参加にとどまった防災集団移転事業。跡地利用は進まず,未だ30%が未利用地。同じく巨費を投じたが空地の目立つ嵩上げ土地区画整理地区。大船渡市や七ヶ浜町の差込式防集など,事業費を抑えながらコミュニティに配慮した優れた事例は評価すべきだが,全体像は生活再建を置き去りにした巨大土木事業の推進だった。退任した遠藤宮城県副知事は,臆面もなく,住民合意の軽視が過剰スペックとなり,モラルハザードを生んだことを述懐する。
「歪められた減災概念 際限なく拡大する土木事業」
「減災」は防護施設に頼ることをやめることだと思ったのは間違いだったのか。「防災から減災へ」の掛け声にも関わらず,巨大土木事業がまかり通った東日本大震災復興。防潮堤復旧指針策定過程の詳細な分析を通じて,遠州尋美さんは,復興構想会議や中央防災会議専門調査会のお墨付きを得て,国交官僚と土木工学研究者の「善意」の暴走が際限のない土木工事の膨張に道を開いたと指摘します。
「事業ありきに縛られた復興計画」
東日本大震災の市街地復興は,従来型手法の大規模な繰り返しに過ぎなかった。一見豊富に思える事業メニューも,活用されたのは防災集団移転促進事業と土地区画整理事業,津波復興拠点整備事業の主要3事業。国交省ガイダンスとパターン調査がレールを敷いた。中でも宮城県ではトップダウンで,被災住民の合意が軽視され,住民意思に反した集約化が意図された。都市プランナーとして復興に携わった阿部重憲さんは,トップダウンの復興事業とコミュニティ本位の復興のせめぎ合いに着目しつつも,持続可能性をめぐる矛盾は今後一層拡大すると警鐘をならす。
「復興まちづくり再考 『職住分離』『高台移転』がもたらした復興の姿」
被災者生活再建支援法の制定につながる世論形成をリードし,国の支援が乏しい中で復興基金を活用して被災者のニーズに応える支援を展開した阪神・淡路大震災の経験に匹敵する独自の成果を東日本大震災復興は築くことができたのか,結局,国が定めた枠組みから踏み出すことなく,被災者を周辺化してオーバースペックな復興にのめり込んだのではなかったか。討論者の田中重好氏の辛辣な指摘を受けて,復興政策の検証のあり方を模索した。
【閉会挨拶】
塩崎賢明(神戸大学名誉教授・兵庫県震災復興研究センター代表理事)
みやぎ震災復興研究顧問・塩崎賢明さんが,2日間の研究交流集会を締めくくります。
共同開催
みやぎ震災復興研究センター/東北大学大学院経済学研究科・震災復興研究センター