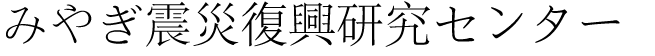「建築とまちづくりセミナー in 仙台」プレ企画・連続講座
第1回 「能登被災地の仮設住宅の実態」(高林秀明さん)のYouTube動画を公開します。
能登半島地震発災以後,能登被災地にて,学生のみなさんと共に継続支援を行ってきた高林秀明さん(熊本学園大学教授)をメインスピーカーにお招きし,「建築とまちづくりセミナー in 仙台」プレ企画第1回として開催した連続講座第1回のYouTube動画を公開します。
開会案内(遠州尋美さん)
講座に先立ち,みやぎ震災復興研究センター事務局長・遠州尋美さんが,主催者である新建築家技術者集団の依頼により,みやぎ震災復興研究センターが開催協力するに至った経過,および,講座のラインナップについて説明しました。
「建築とまちづくりセミナー in 仙台」プレ企画 連続講座
- 2025年7月29日(火)18:30〜20:00
「能登被災地の仮設住宅の実態」高林秀明さん(熊本学園大学教授)
- 2025年8月26日(火)18:30〜20:00
「宮城県美術館現地保存運動の経験」
対談:西大立目翔子さん/高橋直子さん(聞き手:阿部重憲さん) - 2025年9月19日(金)18:30〜20:00
「浜の生活と反原発」佐藤清吾さん(聞き手:窪田亜矢さん) - 2025年9月24日(水)18:30〜20:00
「寂寥たる創造的復興」小川静治さん(東日本大震災復旧・復興支援みやぎ県民センター事務局長)
いずれもオンラインでの開催です。
ミーティングID: 608 220 1785,パスコード:20110311(4回とも共通です)。
なお,10月開催の「建築とまちづくりセミナー in 仙台」(10月25日,26日)にもご参加ください。お申し込みは,こちらです。
基調報告「能登被災地の仮設住宅の実態」(高林秀明さん/熊本学園大学教授)
能登半島地震発生以来,学生とともに毎月1〜2度の頻度で輪島市を中心として能登半島地震被災地を訪問し,被災者支援に取り組んで来られた高林秀明さん。驚いたのは本来単身世帯用として供給されているはずの1Kタイプ(6坪・20m2)に2人で居住する人々が著しく多いこと。熊本地震や熊本豪雨後の仮設住宅ではほとんど経験のない事態でした。以後,入居被災者の過酷なくらしの実態をさまざまな媒体を通して発信するとともに,居住条件の改善の可能性を探求してきました。従来型仮設住宅(運用終了後解体・撤去することを前提として建築基準法の適用除外を受けて供給される住宅)の大半の供給を担ったプレハブ建築協会常務理事,大和リース株式会社代表取締役会長・森田俊作さんとの意見交換した内容にも触れながら,建設型応急住宅改善への思いを詳しくお話しいただきました。
※ 1K2人居住の数値的な裏付けは得られていませんでしたが,『朝日新聞』が2025年7月3日付朝刊で報道し,829世帯に及ぶことが明らかとなりました。同紙電子版記事は,こちらからご覧いただけます(有料記事です。)
コメントセッション
高林秀明さんの基調報告を受けて,田中純一さん(北陸学院大学教授),田中正人さん(追手門学院大学教授),丸谷博男さん(新建・能登地震復興支援本部長),木村吾隆さん(長岡技術大学准教授),岡本祥浩さん(ちゅ今日大学教授)がコメントし,報告者の高林秀明さんもディスカッションに加わりました。
- 田中純一さん:報告にあったような過酷な居住環境で体調を崩す方続出。関連死の発生も懸念されるが,実際に発生した場合に,関連死と認定されずに埋もれてしまう恐れ。また,より大きな住宅に移る希望を持っていても,自分だけが優遇されることに対する気兼ねから声を上げることを躊躇する傾向も。供給されている建設型仮設の仕様は地域を問わず一律。高齢化が進む中高齢者の健康やくらしに配慮した仕様に変えていく必要を痛感している。時間をかけずにすぐにでも実現すべき課題も多く,声を上げていきたい。
- 田中正人さん:能登では建設型仮設ですでに10件以上の孤独死発生と聞く。熊本ではみなし仮設での孤独死が多かったと思うが,能登のみなしは少ないのか,認識されていないだけなのか。その実態はどうか。阪神・淡路以降で共通しているのは,孤独死は高齢者だけの問題ではないということ。概ね半分は高齢者以外。高齢者に限らず全ての入居者のくらしの実態を注視することが必要。
- 丸谷博男さん:(住宅建築費の高騰が復興の障害になっていることに対する建築家としてのコメントを求められて)6月末が,自宅再建か災害公営入居かの意向調査の回答期限。支援対象だった世帯は小規模住宅の再建を望んでいたが,坪160万円という見積もりで断念し公営住宅希望に。被災者の土地・家屋は大規模だから,数世帯が共同でシェアハウス型で再建できる可能性も考えたい。それにフィットする支援制度がほしい。
- 高林秀明さん:(『朝日』が取り上げた2階建て仮設だが,公営住宅に転用するタイプならさらに禍根を残さないかとの問いに)熊本では2戸を1戸に改装して公営住宅化した例もあるが,報道されたタイプは公営住宅化は困難。
- 木村吾隆さん:能登の1Kは,中越や東日本より狭い。トイレ・シャワー・浴槽が1体のユニットだったものから独立して水回りは改善されたが,住戸面積を据え置いたために居室を圧迫。水回りの改善に対応して住戸面積全体の拡張が必要。「避難所→仮設→本設」ではなく,「避難所→本設」というシナリオを描くべき。必ずしもブルスペックではなく,シェアタイプなど,福祉と住まい支援を融合した支援の枠組みなど多様な出口戦略を検討する必要を感じる。
- 岡本祥浩さん:必要数に対して仮設住宅の戸数が著しく過小。現場では優れた取り組みがあっても,それらがバラバラで経験が共有されず,見守り支援との連携も欠如。住宅,ライフライン,生活支援全体を俯瞰的に見て,包括的に展開できる仕組みを築く必要。
- 高林秀明さん:災害救助法一般基準から標準的面積要件が削除され,被災地の条件に応じて仮設住宅の仕様を定めることができるようになったのは,裁量拡大と評価する認識もあるが,それが居住水準の悪化を招くのは本末転倒。最低基準を定める必要を感じる。また,プレハブ建築協会の規格のあり方などについても,率直に意見交換が可能な関係づくりを進めていきたい。
【報告資料】
【参考:能登被災地の仮設住宅に関する意見交換会録画映像視聴ページ】
高林秀明さん,岡本祥浩さんがとりまとめ役となって建築・住宅問題の研究者,住宅運動団体に関わるみなさんをお誘いして2024年11月から2025年1月にかけて意見交換会を実施しています。参考として,第1回および第2回の意見交換会での報告・ディスカッションの録画映像視聴ページへのリンクを掲載します。