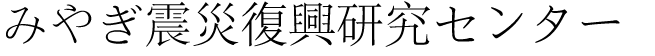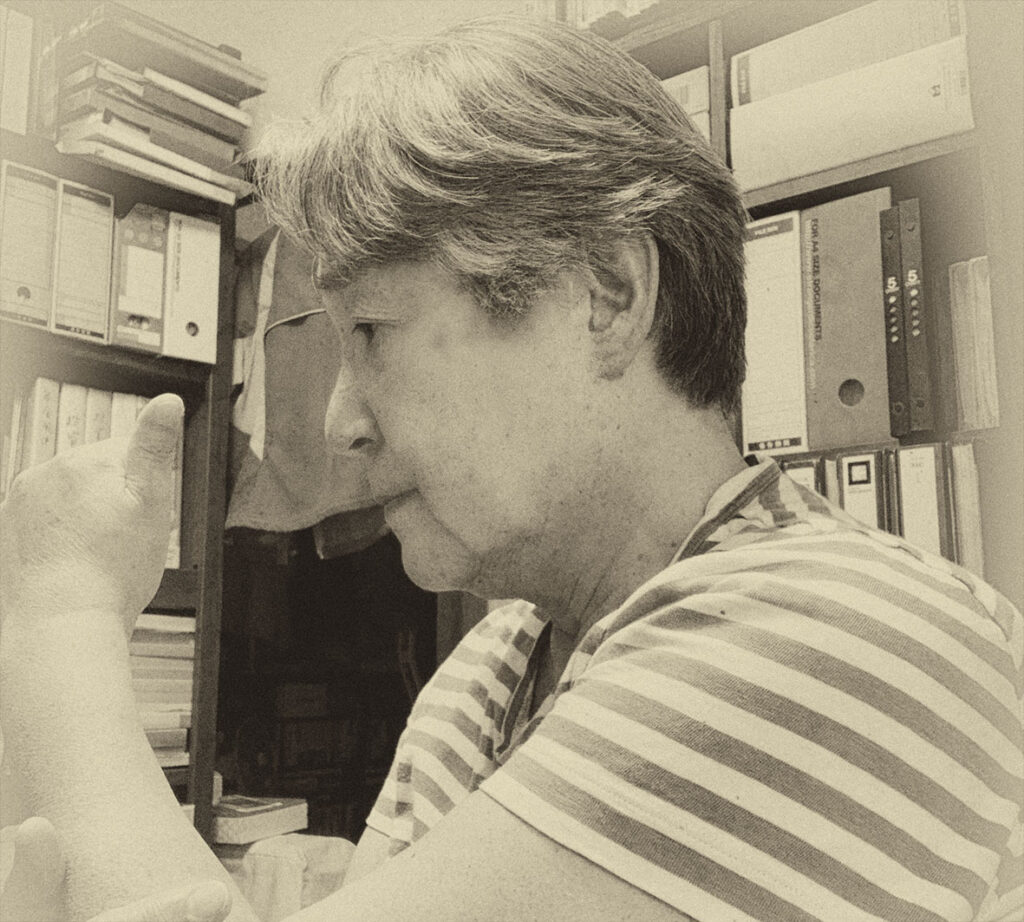住みよい県営住宅をつくる県民の会第2回総会・学習講演のつどい
「くらし,まちの再生と県営住宅」と題して講演しました。
10月4日,住みよい県営住宅をつくる県民の会は,仙台市戦災復興記念館で第2回総会と学習講演のつどいを開催しました。総会に先立って開催された学習講演のつどいでは,私が講師をお引き受けして,「くらし,まちの再生と県営住宅」と題して講演しました。講演を録画しましたので,宮城県による県営住宅廃止と「移転支援」という名目での入居者追い出し問題に関心のある方にぜひご覧いただきたいと思います。
私の講演の要点は,
- 県営住宅廃止方針の唯一の根拠である公営住宅需給バランス推計の欺瞞性
- 需要側では,公営住宅施策対象世帯全体ではなく,その6割に過ぎない「著しい困窮年収未満の世帯数」に需要を限定し,公営住宅施策対象世帯数や限定の事実,理由を示さず,結果として需要を過小評価している。
- 「著しい困窮年収未満の世帯数」は「公営住宅施策対象のうち,民間市場において,自力では適切な家賃負担で最低居住面積水準を達成することが著しく困難な年収以下の世帯」(国総研)であり,公営住宅の提供,家賃補助の実施等の公的支援が不可欠な世帯であることを説明していない。
- その世帯数は,県内の公営住宅戸数を4万世帯超過しているが,その支援をすることなく,さらに県営住宅を廃止しようとしている。
- 国総研推計プログラムは,現実に最低居住面積水準を満たしていない世帯(過密居住世帯),適正家賃負担率を超える高家賃を負担している世帯(高家賃負担世帯)の数も自動的に推計する。2025年時点で,両者合わせて3万世帯を超えているが,県はその結果を公表せず,従って一才の支援を放棄している。しかも,県が需要とはみなさない困窮水準以上の世帯においても,過密居住世帯が6千世帯,高家賃負担世帯が2千世帯存在し,困窮ライン以下の世帯のみを需要とする正当性が揺らいでいる。
- 「過密居住世帯」「高家賃負担世帯」は,20年後の2045年にも合計2万7世帯存在すると推計され,仮に県の主張通り需要を供給が超過していても,市場に委ねては住宅困窮が解消されないことを示すものであり,県の論理の破綻を証明するものである。
- 他方供給側においても,需要に適合する供給数として,生活保護制度における住宅扶助額を下回る家賃の借家数と定義するのは,明らかな課題評価である。国民年金以外の所得のない単身世帯が住宅扶助相当家賃を負担すれば,それ以外の可処分所得は月額3万円を下回ることになり,生活できないことは自明である。需要に適合する供給数は,公営住宅家賃を下回る家賃の借家数でなければならない。
- 生活扶助額以下の家賃の借家に居住可能なのは,生活保護受給者であり,それをあえて供給数として需給バランスと主張することは,住宅困窮者が全て生活保護を受給するとい前提にたつものであって,非常識かつ非現実的である。保護費の地方負担分を負う基礎自治体の支持を得られるものではない。
- 住宅セーフティネットにおける公営住宅の意義
- 住宅確保要配慮者は今後も増加:公営住宅で完全対応は不可能で民営借家への受け入れ拡大は不可欠
- 家賃が高い登録住宅(家賃3万円未満は0.5%,宮城県0.25%)
- 払拭できない受け入れへの躊躇:家主・管理会社の7割が高齢者・障害者に忌避感
- 現状では既設公営住宅の活用が最も効果的な要配慮者対策
- 公営住宅の認識に関する誤解をただす
- 民業圧迫論の誤謬:公営住宅の入居者属性と民営借家の入居者属性は全く異なっており,市場の競合はない。民営借家の数は,公営住宅をはるかに凌駕しており(7.5倍),公営住宅が多少増えても,影響しない。
- 公営住宅に国が税金を投入するのは,法(公営住宅法)の定められた国の義務。県営住宅建替事業が税金の無駄遣いであるかのような言説は,法を蔑ろにするもので行政の長としての資質が問われる。
- 県営住宅建替事業に国税は支出しても,地方税の支出は一切なく,一般財源には全く負担が生じない:建設費の45%は国庫補助,地方負担分(55%)は地方債で調達,償還は家賃収入。維持管理費も家賃収入でカバー。
- 公営住宅建替事業の財政効果
- 公営住宅建替事業収支は,35年目ごろから累積黒字,以後家賃収入分が積み上がり,定期的な補修や大規模修繕,70年運用後に建て替える際の除却費を賄ってなお黒字になる(国交省試算)
- 介護・医療費削減効果:バリアフリー化,福祉対応住宅化,エレベータ設置による介護費用の削減。省エネ住宅化(温熱環境の向上),エレベータによる外出のしやすさと社会参加機会の向上が心身の健康増進につながり,医療費削減が期待できる。
- 公営住宅建替事業の地域経済への貢献
- 公営住宅建替事業は,国庫補助事業として確実に実施可能(他の公共事業は建設工事単価の急騰で実現性は不透明)
- 公営住宅建替事業の経済波及効果は極めて大きい
- 居住人口の維持による地域商業への貢献
- 公営住宅団地の建替に伴う地域拠点施設の併設は,地域単位での住宅施策と福祉施策の連携推進を求める国の施策の重要課題=県民の会の要求に合致
- 住宅セーフティーネット制度の国交省・厚労省共同所管化
- 住生活基本計画における子育て環境,多世代相互支援環境を充実させるまちづくりの推進目標:実現手段は,住宅団地建替や再開発に伴う拠点施設整備
- 公的賃貸住宅団地(100戸以上)の建替伴う,子育て・介護・医療・地域交流拠点施設整備は建替事業の一部として国庫補助対象。